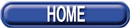50MHzクリコンの基板と同じ基板を用いるように設計しました。
一部の部品を交換することでSSB用プロダクト検波器に早変わりします。
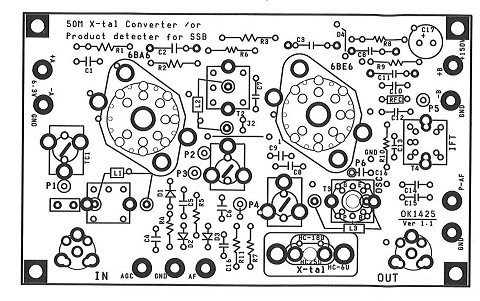
部品を取り付けた状態
<特徴>
① 勉強しながら製作ができる
② 真空管の作る実感が味わえる。
③ 機械加工が必要なくラジオパーツで作る
<製作について>
<ブロックの構成>
・ラジオ用真空管を用い中間増幅 455kHzを6BA6、BFOを6BE6 計2本
でSSB用プロダクト検波器を構成しております。
・中間周波数は、455kトランス(T1)と(T2)で決定し、BFOは、6BE6の
発振は、455kトランス(T3)により発振させいます。
・プロダクト検波のLSBとUSBは、外部に豆バリコン(10p)をP4-GNDに
接続して手動でチューニングをする。
・オプションとして中間周波増幅後、AM検波とAGCの出力端子を設けている。
<部品取付>
・回路図と部品配置図を参考に部品を半田付けしてください。
・BFOのT3トランスの接続は、回路図面のとおり1次コイルと2次コイルを間違わないように基板に
差し込む。(T3の3ピンの方が真空管側に挿入する。逆に取付けると発振しません。)
・抵抗は、熱くなることはありませんが、基板より浮かせて取付けてください。
・再度、取付けミスがないか確認しておいてください。
<電圧のチェック>
・真空管を差し込まないでA電源とB電源を接続して管ソケットの3・4ピン間にA電圧、5・6とGND間
にB電圧がかかっていることを確認する。それ以外の端子に電圧がかかっていないことを確認して
おいてください。
・つぎに真空管を差し込んでヒ―タが点灯、5・6とGND間に所定の電圧になることを確認する。
<BFOの発振>
・ラジオを用意し、このユニットに近づけるとBFOの455kの発振がするか、 、T3のコアーを回して
調整してください。また、外付け豆バリコンを回すと発振音が変化するか確認すること。
<調整方法>
・入力側に455kHzの信号(-50dBm程度)を入力し、プロダクト検波出力の強度を T1、T2の
コアーを回して最大になるよう調整する。(検波器出力にオーディオアンプをつないでおくとよい)
<収容ケース>
・収容ケースに収める場合は、入力端子をしっかりとケースに取付ける。
また、真空管の熱流にも注意を払ってください。
・収容ケースに、外付け豆バリコン(20p)を P6-GND間に取り付けLSB,USBのチューニング
出来るようにする。
<回路図>
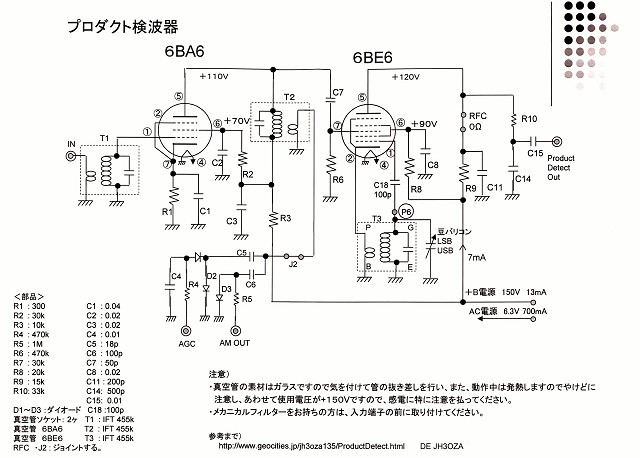
<組立順とその調整方法>
<調整>
<>
<性能>
1) SSB復調 入力-90dBmで復調
2) AM復調 入力 -30dBm s9
3) AGC 入力 -20dBm -4V
-30dBm -1V
-40dBm -0.2V
<感想>
この製作にあたり近くに住んでいるOM JA1DWO鈴木さんには、お世話になり感謝しております。
By JH3OZA
2014/5/1